物理・化学プログラム
研究の紹介
|
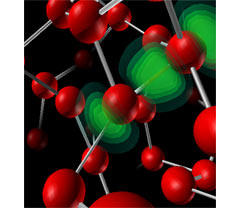 シミュレーションによる液体中の化学結合 |
|
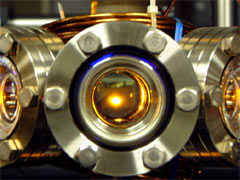 レーザー冷却された、ナトリウム原子群 |
|
 超伝導現象におけるマイスナー効果 下に並んでいるものが強力な磁石。浮いている黒い物体が超伝導体 |
|
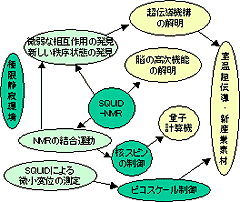 シミュレーションによる液体中の化学結合 |
|
 単結晶自動X線解析装置
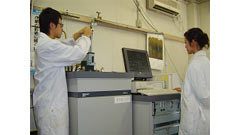 SQUID磁束計
|
|
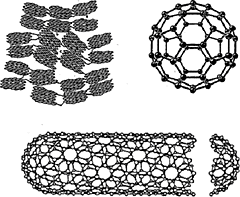 シミュレーションによる液体中の化学結合 |
|
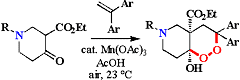 シミュレーションによる液体中の化学結合 |
||||
|
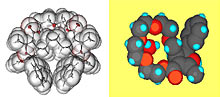 合成された17員環大環状化合物
|
|
|